1分でわかる忙しい人のための韋昭(韋曜)の紹介
韋昭(いしょう)、字は弘嗣(こうじ)、出身は呉郡雲陽、生没年(201年~273年)
呉の史学者・経学者であり、『呉書』を編纂したことで知られる人物である。
若年のころから学問を好み、文章に秀でた。太子孫和に仕えた際には、賭け事に熱中する蔡穎を戒める文を上奏し、勤学の重要さを説いた。その論文は当時高く評価された。
孫亮の治世には太史令として『呉書』を編纂し、孫休の時には博士祭酒として国学を統括した。劉向に倣い書籍を校定するなど、学問行政の整備に尽くした。
しかし孫皓の即位後は諫言がたびたび容れられず、父孫和の本紀を立てることに反対したため不興を買った。晩年には著書「洞紀」「官職訓」「辯釋名」を完成させたが、鳳凰二年(273年)に獄死。享年七十三。
『三國志』の陳寿も韋昭の『呉書』を参照しており、その記録精神は後代の史家に受け継がれた。
韋昭(韋曜)を徹底解説!東呉の学術を支えた史学者とその悲劇的最期
学問に励む若き韋昭
韋曜、本名は「韋昭」だが後に晋の司馬昭と名が被ってしまい、あちらが天下を握ったせいで、こちらは曜に改められて史書に残っている。
以降、韋昭で進めていく。
彼は若き日から、文章の才能に恵まれ、筆に取り憑かれていた。食事中にも筆を離さなかったとか。 伝説じみた話すらあるが、実際に学問に明け暮れていたのは確からしい。
その才が認められ、まずは丞相掾、西安令として地方行政を任されると、堅実に政を治め、中央に召されて尚書郎に。さらに太子中庶子として太子・孫和の教育係に抜擢された。
蔡穎と東宮での論争
太子中庶子として東宮に仕えていた韋昭の職場には、蔡穎という同僚がいた。これがまた、勉強そっちのけで賭け事(囲碁や双六)に夢中という、知の場における娯楽担当のような人物である。
当然ながら、そんな姿勢に眉をひそめたのが太子・孫和だった。「これでは風紀が乱れる」と判断した太子は、真面目一徹の韋昭にペンを取らせ、諫めの文を作らせることにした。
韋昭は「真に立派な人物は、年を重ねても功も名も得られぬことをこそ恥じるもの」と切り出し、古今の賢人たちを例に引いて、若き日の学びの重要さを説いた。
さらに賭け事に熱中する者は心を見失い、節操をなくすと書き連ね、蔡穎の遊び癖をピンポイントに爆撃した。
韋昭は、学問こそが人の名誉を築くものであり、勝ち負けの遊びなどに価値はないと結論づけた。
この文章は東宮で大きな評価を受け、彼の学識と文章力が世に知られるきっかけとなった。 一方の蔡穎がどう反応したかは記録にないが、盤の駒が涙で滲んだ可能性は否定できない。
太史令として『呉書』を編纂
建興元年(252年)、孫亮が即位すると、政権を預かった諸葛恪は「国の記録がグダグダでは体面が立たぬ」と判断し、筆の力で信をえる韋昭を太史令に任じた。
韋昭はこの職を拝し、正式な国史『呉書』の編纂にあたった。
この国家的な一大事業には、華覈や薛瑩といった頭脳派の面々も巻き込まれた。
彼らが史料を掘り起こし、諸臣の発言や政局の推移を細やかに記録しながらも、筆致は冷ややかで過不足がない。
誰が失脚しようと、誰が寝返ろうと、韋昭の記録は「はい次」とばかりに淡々と進む。あまりの冷静さに、書かれた側が読んだら魂が抜けるレベルである。
こうして生まれた『呉書』は、呉という国の正史として初めて全貌を捉えた書物となった。
※史通によると、華覈が孫権の時代から始まった呉書編纂メンバーを上奏して呼び戻し、事業を再始動させたとなっている。
孫休期の国学創設と博士祭酒
永安元年(258年)、権臣・孫綝が皇帝孫亮を廃し、孫亮の兄の孫休を即位させるという政権シャッフルが行われた。孫休はまず年号を永安とし、治世の目玉として「文教の刷新」をぶち上げた。
その目玉政策が、五経博士の設置と国学の創設である。いわば官製の学問インフラ整備であり、これが後の南京太学へとつながる初の中央学府だった。
この新設学府の責任者として任じられたのが韋昭で、彼は中書郎と博士祭酒を兼任し、教員兼学長として校舎の設計からカリキュラムまで丸ごと担当する羽目になった。
前漢時代の劉向を参考にして、書籍の校定と文献の整備を命じられ、乱世で散逸した典籍をかき集め、章句を補い、誤字を正し、あらゆる文献に校閲のメスを入れる。
この「文書の再建工事」により、呉の学問はやっと制度としての骨格を持った。
張布との対立と侍講拒否
国学の頂点・博士祭酒に就いた韋昭に対し、孫休はさらなる期待を寄せた。
「この男の講義を自ら聞こう」とばかりに、韋昭や盛沖を宮中に招き、経書や史書の進講を命じようとしたのである。
ところが、張布がこの動きを全力でブロックした。理由はシンプルで、韋昭みたいな口うるさい学者が皇帝の耳元で、あーだこーだやれば、自分の実力がばれて、専権を奪われるかもしれない、という猜疑心が爆発し、全力で潰しにかかった。
孫休はこれに不快感を示しつつも、強行はできなかった。結局、韋昭も盛沖も宮中で語る場は設けられず、計画は頓挫する。
当の韋昭はこの一件を深追いせず、著述と教育に専念した。br /> 政治に担ぎ上げられる道を断ち、学問に腰を据える選択は、このとき固まったとも言われる。
孫皓の即位と封爵・官職
永安七年(264年)、孫休が崩じ、孫皓が呉の皇帝として即位した。
孫皓は当初こそ文治主義を掲げ、学者官僚に期待を寄せた。韋昭はその筆頭として、高陵亭侯に封じられ、中書僕射・侍中に任ぜられ、さらに左国史も統括するという三冠王に抜擢された。
彼の任務は、要するに「記録と管理と雑用全部」である。引き続き国の歴史を記し、文書を整え、皇帝の耳元で「これはそういう意味ではありません」とささやく係でもあった。
そんな中、各地から「瑞応」という不思議な現象が報告された。孫皓はそれを吉兆だと大喜びし、臣下に意味を聞いて回る。
そこで韋昭はあっさり一言、「それ、家筐篋中物(ただの家財道具です)」と答えた。
神秘を求める皇帝に、科学的冷や水をぶっかける学者が当然、喜ばれるはずもない。
こうして韋昭は、筆の重みで信を得た男から、空気を読まぬ者として、徐々に孫皓の寵愛リストから外されていく。
主君との不和と諫言
孫皓の治世下でも、韋昭は変わらず中書僕射・侍中・左国史の三役を担っていた。
だが次第に、主君と臣下の認識のズレが広がっていく。ほころびはやがて裂け目となり、後に取り返しのつかない断絶へと育つ。
発端は、孫皓が父・孫和を正式な皇帝として祀ろうとしたことだった。
「父上にも本紀を」と言い出した皇帝に対し、韋昭は「帝位に即いていない以上、それは列伝が妥当です」と進言する。 冷静かつ理性的だが、理屈はいつも感情に敗れる。
孫皓は「逆らった」と受け取り、怒りを溜め込む。
以後も韋昭は記録と制度の正しさを守る立場を貫き、折れぬ筆先でたびたび諫めを行った。誠意を尽くしたつもりが、「誠意が足りぬ」と叱責される。
心折れた韋昭は、老衰を理由に辞職を申し出て、著作の完成に専念することを願い出たが却下。
代わりに与えられたのは、自由ではなく監視だった。もはや両者の間に言葉は届かず、筆だけが浮いた。
暴君の酒宴と韋昭の苦悩
韋昭はいまだ中書僕射・侍中・左国史の三職を兼ねていたが、その肩にのしかかるのは政治の重責だけではなかった。
主君・孫皓の饗宴主義もまた、彼の神経をじわじわ削っていった。
宴は朝から晩まで続き、群臣には七升の酒が義務付けられる。
韋昭は元より酒に弱く、二升が限界だったが、当初は特別に茶を賜る配慮もあった。しかし帝の関心が別に移ると、背信と見なされるようになる。
やがて宴の場は、酔った皇帝による「断頭クイズ大会」と化す。
酔った後に侍臣がだす難題に答えられねば拘束、失言すれば即処刑という、酒と知識を使った恐怖の宴会である。
韋昭はそれを「名誉を損ない、怨みを積むだけ」と見抜き、経書に即した答弁のみで応じたが、それがまた「詔命を軽んじた」とされ、怒りを買う。
こうして積もりに積もった不興が、鳳凰二年(273年)、ついに彼を獄へと引きずり込んだ。
最期の上疏と悲劇的な死
獄に下された韋昭は、なお筆を手放さなかった。
自らの罪を詫び、主君の恩に言及しつつ、長年の著作を捧げる一通の上疏をしたためた。
「古来の歴注には虚実入り混じる。我は伝記を照合し、異同を検討し、耳目の及ぶところを採りて《洞紀》三巻を編む。庖犧より秦漢に至る歴史を記し、さらに黄武以降の一巻を加えようとす。
また、劉熙の『釋名』を読み、長所を取り入れつつ誤りを正し、《官職訓》《辯釋名》を撰述した。これらの書を秘府に納めたく願う。」
死を目前にしても、記録の責を離れず、紙上に理と節を刻み続けた彼の姿は、筆の下に命を置いた文人そのものだった。
しかし孫皓はこの上疏に、「書が汚れているのはなぜか」と問い詰めた。
韋昭は「幾度も読み返し、手が震え、誤って点を汚しました」と答え、叩頭五百、両手を床に打ちつけて赦しを請う。だがその姿に心を動かされることはなかった。
このとき、同じ学者の華覈が涙ながらに上疏した。
「韋昭は呉の司馬遷なり。古今に通じ、儒学に明るく、その史才は群臣に並ぶ者なし。かつて漢の武帝は司馬遷を赦し、史書を成らしめたり。陛下もまた、この才を惜しまれよ。」
さらに彼は「『呉書』は既に骨格を得たが、いまだ総評と結びの章が整っていない。もし韋昭を失えば、この書は不朽を欠く」として、赦免と筆の完成を願い出た。
だが、孫皓の怒りは終始変わることなく、獄につながれた同年の鳳凰二年(273年)に韋昭は誅殺された。その一族百家は零陵に流され、筆の業と共に命までもが裁かれた。
この死は、学問に殉じた一人の文人の最期であり、暴政を映した悲劇であった。
それでも史書は、なお「子の韋隆もまた文に優れたり」と記す。
韋家の血が、知の灯を絶やさぬまま、次代へとつながったことを証している。
文人としての評価
陳寿は『三國志』の評で、薛瑩曰く「学問に熱心で古典を好み、広く書籍を読み、記録・編纂の才能に優れた人物である」とされる。
また、胡沖は「華覈との比較においては、文賦の才では劣るが、典誥(制度文書)においては勝る」とされている。
彼は清廉な士人たちと並ぶ存在として名を挙げられており、激動の時代にあって高位に登りながら、理不尽な死を遂げた彼に対し、陳寿は皮肉を込めてこうも書いた。
「むしろ死を免れた者こそ幸運であった」
彼が編んだ『呉書』は、後に陳寿自身が『三國志』を著す際の礎となり、呉国の記録体系を初めて形にした史書であった。
生前、華覈が「呉の司馬遷」と称したその筆は、事実に忠実で、古典と経史に通じ、誤謬を正して真を求める姿勢に貫かれていた。
学問に殉じ、筆に生き、筆に斃れたその人生は、まさに儒者の終着点である。
参考文献
- 三國志 : 呉書二十 : 韋曜傳 – 中國哲學書電子化計劃
- 三國志 : 呉書七 : 步隲傳 – 中國哲學書電子化計劃
- 三國志 : 呉書八 : 薛綜傳 – 中國哲學書電子化計劃
- 資治通鑑/巻078 – 维基文库,自由的图书馆
- 資治通鑑/巻080 – 维基文库,自由的图书馆
- 史通 : 巻十二 – 中國哲學書電子化計劃
- 参考URL:韋昭 – Wikipedia
韋昭(韋曜)のFAQ
韋昭の字(あざな)は?
字は弘嗣(こうじ)です。
韋昭はどんな人物?
学問を愛し、真実を重んじた学者です。権勢に屈せず、儒者としての信念を貫きました。
韋昭の最後はどうなった?
鳳凰二年(273年)、孫皓との確執から獄に下され、誅殺されました。享年七十三です。
韋昭は誰に仕えた?
孫権の子孫である孫和・孫亮・孫休・孫皓の四代に仕えました。
韋昭にまつわるエピソードは?
博奕を戒めた太子論は有名で、勤学と礼を説く儒者の鑑とされました。
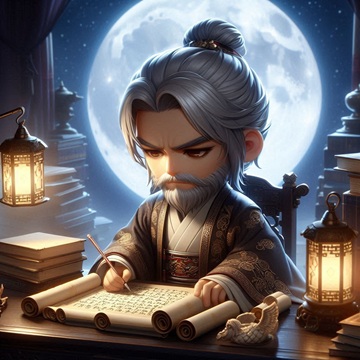






コメント