1分でわかる忙しい人のための赤壁の戦いの紹介
赤壁の戦い(せきへきのたたかい)は、中国の後漢末期における最大規模の水上決戦である。
時は建安十三年(208年)、中原を制した曹操が南方進出を図り、荊州を制圧。その勢いのまま、江南の孫権を攻めようとする。
対する孫権は、諸葛亮の説得を受けて劉備と連合。周瑜を総大将とし、赤壁で迎え撃った。
周瑜は曹操軍の弱点を見抜き、黄蓋と仕組んだ火計で大軍を焼き払うことに成功。曹操は退却を余儀なくされ、中原と江南の境界線は維持される。
この戦いは魏・呉・蜀の三国鼎立を決定づける分岐点となった。
赤壁の戦いを徹底解説!三国時代の分水嶺、その全貌
前哨戦:荊州陥落と長坂坡の敗走、劉備、追われる民の守護者となる
建安十三年(208年)、荊州の牧・劉表が死去すると、後継の劉琮は、曹操の進軍に抗うことなくあっさりと降伏した。
この判断は政略的には妥当だったかもしれないが、劉備には一切の相談もなかった。
まるで会議に呼ばれず、いきなり稟議書の控えだけ回されたような仕打ちである。
劉備は退却を余儀なくされるが、問題はその同行者だった。
軍勢というより、民衆の避難行列。武装した兵よりも、家財を背負った家族の方が目立つ。
逃げるには重く、守るには多すぎる。
しかし、これを捨てなかったのが劉備であり、だからこそ“仁”を語る余地が生まれた。
曹操は、そんな人道主義を待ってはくれない。
荊州を制圧した勢いそのままに追撃をかけ、劉備軍を長坂坡で捕捉する。
趙雲が劉備の子・劉禅と甘氏を救い出し、張飛は橋を落として時間を稼いだ。
このときの橋上の睨み合いは、数の差を戦意で埋めた典型例である。
最終的に、劉備は夏口へ退き、江夏にいた劉琦と合流した。
一連の敗走劇は、軍略としては後手に回った失策かもしれない。
だが、”敗れても慕われる”という、彼の異質な資質が際立った場面でもある。
赤壁はまだ始まっていない。それでも、劉備の物語はすでに始まっていた。
荊州を掌握した曹操、次なる目標「江東」へ
長坂坡の追撃をひとまず切り上げた曹操は、江陵へ進軍するとすぐに「荊州吏民、与之更始」と布告。
過去の立場も罪も問わず、再出発を共にしよう。という建前の下、荊州の再編が始まった。
実際には“寛容な顔したスカウト活動”であり、参加しない者は事実上の切り捨て。
その呼びかけに応じた者には甘い飴が与えられ、侯に封じられた者は十五名、名士も次々と取り込まれていく。
荊州が掌中に収まると、次に動いたのは益州の劉璋。
三百人の使者を送り、「懲役をお受けします」と丁寧に頭を下げてきた。
まだ戦ってもいない相手に白旗。見事な事なかれ主義である。
この時、唯一ブレーキを踏もうとしたのが賈詡だった。
「まずは新領地を安定させてから」と至極真っ当な助言をするが、曹操は聞き流す。
言ってみれば”年末進行”の現場に「一回落ち着きましょう」と言うようなもの。
休む気配はゼロ、むしろ今がチャンスとばかりに水軍の整備を進め、東征を準備し始める。
江陵は曹仁に任され、曹操は本隊を率いて江東方面へ出陣。
その動きを見た劉備は、夏口に拠点を移しつつ、諸葛亮を孫権のもとへ派遣する。
魯粛の引率で柴桑へと赴き、江東との交渉ラインを開こうとした。
ちょうどその頃、孫権のもとには曹操の勧降文が届く。
「近者奉辞伐罪、旄麾南指、劉琮束手。今治水軍八十萬軍,方與將軍會猟於呉。」
訳せば、「最近、天命に従って悪を討ってます。ついでにあなたの領土で“狩り”をしませんか?」。
要するに、降伏しろという名のラブレターである。

孫権の逡巡と決断:降伏派と抗戦派、ひとつの椅子をめぐる攻防
曹操の影が柴桑に迫ると、呉の朝議は一気に”白旗ムード”に染まった。
張昭、秦松らは揃って「曹操は漢の丞相、これに刃向かえば逆賊」と唱え、降伏一択と訴えかける。
「曹操は荊州水軍を手中に収め、長江の防壁など役に立たぬ」
つまり、戦う前から諦めた者たちが、綺麗な言葉で膝をつく準備をしていたのである。
この”土下座大会”をぶち壊したのが魯粛だった。
孫権が便所に立った瞬間を見計らって追いかけ、手を取って言う。
「彼らの言うことなど、天下を語るには足りません」
「曹操に降れば、私は郡守にでもなれましょう。では殿は? 一度、国を治めた者が、あの男の下に座る椅子など残っているのか?」
孫権は深く頷き、「張昭らは、まったく期待外れだった」と吐き捨てる。
魯粛はすかさず「劉備との連携を」と提案し、周瑜を呼び戻す手配も進められた。
一方その頃、諸葛亮も同じテーマで孫権と対峙していた。
孫権が問いかける。「なぜ劉備は降らぬのか」
諸葛亮は間髪入れずに答える。「田横(春秋戦国時代の将)ごときでも節を守った。
劉備は王族の血、英雄として人望を集めている。
たとえ敗れようと、民は彼に従い続ける。敗軍の将ではなく、志を貫く指導者として」
そのうえでこう加える。「水軍に関羽、江夏に劉琦、精兵あわせて二万は残っている。まだ勝負になる」
さらに諸葛亮は曹操の弱点を列挙する。
「北方兵は水に弱く、遠征続きで疲弊している。荊州も完全には心服していない。
疫病が流行し、兵士は水土に馴染めず病に伏す」
孫権はうなずき、「全呉を挙げて曹操に従うなど、まっぴらごめんだ」と明言。
「対抗できるのは劉備しかおらぬ」と口にしたとき、ついに呉の命運は定まった。
その直後、周瑜が急ぎ戻る。彼もまた、魯粛と同じく戦うべしと主張。
「曹操を破れば、天下は三分。荊州上流は呉のものになる」と。
彼の読みも鋭い。馬超・韓遂が西方に健在、寒さで馬が干上がり、水戦にも馴染めぬ中原兵など、戦う以前に崩れると見抜いていた。
「曹操は漢を語るが、実は賊そのもの。孫将軍は正統な英雄、なぜひれ伏す必要があるのか」
周瑜の言葉に、孫権は完全に覚悟を決めた。
孫権、決断の一刀:机を断ち、賭けるは呉の存亡
「三万の精兵をくれれば、曹操なんぞ叩き潰してみせましょう」。
そう啖呵を切ったのは、他でもない周瑜だった。
この進言を受けた孫権は、どこか待ちかねていたように応じる。
「曹操め、漢室を倒して自立を目論んでおる。二袁も呂布も劉表も倒された今、残るはこの私ひとり。やるしかあるまい」
そして、衆人の面前で卓を一刀両断。「曹操を迎えよ」と口にした者がいれば、この卓と同じ末路だと、明確な意思を示した。

さらにその夜、周瑜は再び孫権に謁見し、曹操軍の実態を分析する。
「八十万? ハッタリです。実数はせいぜい二十数万、しかも疲れ切っていて疫病まで蔓延。
加えて、劉表配下だった連中は忠義に欠ける。数が多くても、それは紙風船のような軍です」
孫権は満足げに周瑜の背を叩き、「子布や元表は家族のことばかり。おまえたち二人だけが、私の胸の内を察してくれる」と語った。
三万の兵と共に、周瑜・程普を都督に任命。魯粛を副官とし、黄蓋、甘寧、呂蒙、凌統など実力派ぞろいの面々が出陣準備を整えた。
一方その頃、曹操陣営では「孫権は劉備を始末するだろう」との読みが主流。しかし軍師・程昱だけは違った。
「孫権はまだ若くて全国的な威厳が足りん。今こそ“劉備ブランド”を借りて対抗するはず」。
予想的中、曹操側の“誤算”がじわじわと、運命を赤壁へと導いていく。
火と風と偽装と:赤壁で焼かれた曹操の夢
周瑜が率いる水軍は長江を南岸から進軍、劉備は陸路で樊口に布陣した。
水陸両軍が赤壁で合流すると、ついに曹操軍と対峙する。ここが歴史の分岐点となる。
曹操軍は荊州で降伏させたばかりの兵と、新たに編成した水軍を抱えていたが、いかんせん、まとまりに欠ける烏合の衆。それに加えて、移動中に疫病が発生。
体力も士気も底を突きかけた軍隊にとって、長江はもはや「天然の防壁」ではなく、「水辺の難所」と化していた。曹操は仕方なく軍を江北に退き、船を烏林の北岸に停泊。
ここで動いたのが、呉の古参・黄蓋だった。彼が提案したのは、
「曹軍の船、首尾が繋がってる。そこに火を付ければ一気に燃え広がる」というシンプルかつ大胆な作戦。
周瑜は即決し、黄蓋に偽降作戦を命じる。敵の懐に近づき、火を放つ、まさに命がけのスタンドプレーである。
決行の日、黄蓋は軽快な蒙衝船十艘を用意。薪と油を満載し、
外装を赤い幕で飾り、旗と龍幡を立てて堂々と進む。
ちょうどその時、東南から強風が吹いていた。追い風に帆を立て、
黄蓋はたいまつを手に、「そっちに降伏しまーす!」と叫びながら接近する。

曹操軍の兵士たちは、敵軍の動きを一種の見世物のように眺めていた。
「おいおい、黄蓋が降ってきたぞ」と呑気に指差していたその刹那、黄蓋は薪に火を点ける。炎は風に煽られ、船はあっという間に突入。
瞬く間に北岸の船団を包み込み、炎は岸の陣地にも達する。
「煙と炎が天を覆い、人馬が焼け、溺れる者が続出」
赤壁が本当に赤く染まった瞬間だった。
黄蓋自身は流れ矢に当たり川に転落、兵たちにも認識されず、一時は雑用部屋の床に寝かされるという、戦場とは思えぬ喜劇的な一幕も挟みつつ、韓当に発見・救出され命を取り留めた。

その機を逃さず、孫権・劉備連合軍は太鼓を轟かせて江を渡り、火と鼓動の嵐で曹操軍を圧倒。曹操は戦況が覆せぬと判断し、残存の船を自ら焼き、撤退を決断する。
その後、周瑜と劉備はさらに水陸両面で追撃をかけ、曹操は華容の小道を抜けて雲夢の湿地を越え、江陵へ退却。
途中の道は泥濘で、やむなく弱兵を詰め物にして道をならすほどの窮地。
死者は多く、まるで軍ではなく難民の行進のようだった。
江陵に辿り着いた曹操だが、後方の不安から最終的に北へ帰還。
赤壁での大敗は、まさに彼の“天下取り”構想を焼き尽くした火計であった。
赤壁の戦いの勝因と曹操の敗因:疫病、風向き、そして慢心
曹操、勝てると思っていた。いや、勝てると“思い込んで”いた。
「奉天子以令不臣」という政治的な正統性、北方を制圧した勢い、数の上でも圧倒的多数。
条件だけ並べれば、負ける理由なんて見当たらない。むしろ、勝たない理由がないほどの盤石体制。
それでも負けた。それもボロ負けだった。
敗因の一つは、曹操の慢心と判断ミスだ。「勝ち馬に乗れ」とばかりに集まったばかりの兵士たちは、言わば“レンタル軍団”。
周瑜や黄蓋のように練度の高い軍ではない。さらに、荊州に入ってから病気が流行、兵の多くが疲弊していた。
これが後に「赤壁疫病説」として血吸虫病の関与が議論されるほどの惨状だったというのだから、しゃれにならない。
感染経路、発症時期、免疫差……と分析がなされているが、簡単に言えば「南の風土に慣れてない北方兵」がバタバタ倒れた、ということ。
さらに特筆すべきは「風」。東南風である。火攻めを仕掛ける側にとって、これほどの好条件はない。
その風は、山と湖の地形が作り出した“天然の扇風機”。
曹操にとっては予測不能な“自然兵器”だった。おかげで黄蓋の火船は北岸に一直線。烏林の曹軍はまるで“燻製工場”の中身のように燃え上がった。
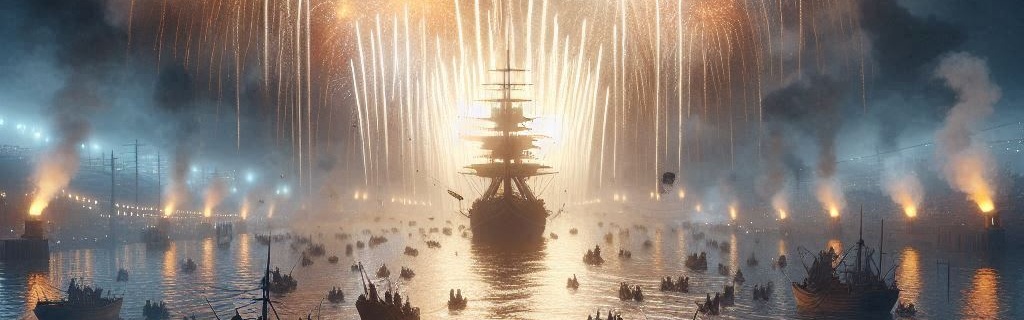
戦線配置のミスも痛かった。烏林一点に戦力を集中させたせいで、火計の一撃に全軍が巻き込まれた。
これが後々の魏軍南進に尾を引く要因となる。対する周瑜は水陸から兵を分散展開し、劉備と呼吸を合わせた作戦で“コーナーからのクロス”を決めた。
ただし、後世の歴史家の中には、「曹操の赤壁侵攻のタイミング自体は悪くなかった」と見る者もいる。
裴松之は「天運の差」と割り切る。いや、割り切りすぎだろう。
ともかくも、この“歴史のジャイアントキリング”によって、以後の南方攻略は大きく遅れる。
そして、曹操はこの敗北を「郭嘉が生きていれば」と嘆いた。
戦に勝てば「天運」、負ければ「死人の知恵」。いつの世も、負けた将軍はそう言うものだ。
参考文献
- 参考URL:赤壁の戦い – Wikipedia
- 資治通鑑 卷六十五 – ウィキソース
- 陳寿『三國志』
- 裴松之注
- 江表伝
- 張作耀『曹操傳』



コメント